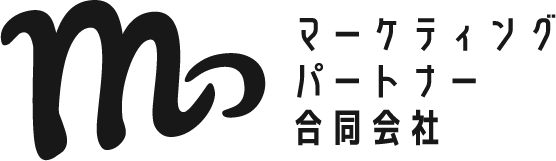・オンライン検定の全体像が把握できる
・使っていく検定システムの特徴がわかる
・設問作りの“肝”がわかる
私たちチームエアでは、オンライン検定の構築&運営のサポートを行なっておりますが、今回の記事はその中で培ったノウハウやシステム構築のポイントをまとめたものになります。
うまくいった経験だけでなく、失敗した経験も含めてまとめていきたいと思いますので、これからオンライン検定を作ろうと思われている方には参考にしていただけると思います。
さて、世の中には様々な「〇〇検定」がありますがその中でも、世の中で一番知られている検定は「漢検」「英検」ではないかと思います。
早い人は小学校低学年から受検する検定で、級保有者は高校受験などで優遇されるなどメリットもあるので受けたことがある方も多いのではないでしょうか。
また、「〇〇検定」にはエンタメの要素も含まれているものもあり、「日本酒検定」や「ワイン検定」など趣味を深く勉強するためのものとして人気の検定もあります。
本屋さんでも検定用の参考書がたくさん売っています。最近では「チョコレート検定」が人気のようで本屋さんでも大々的にプロモーションされていました。
ちなみに、ソムリエのように趣味として資格を取るのではなく仕事に活かすために取得するものもありますが、今回解説するオンライン検定はそこまでしっかりとした資格、検定を作る前段階に適しており、気軽に検定を作りたいという方やエンタメ要素を入れてノウハウ広めていきたいという方におすすめの内容になっています。
もちろん、オンライン検定を集客ツールとしてビジネスに活かす方法にも触れているので、参考にしていただければと思います。
オンライン検定をおすすめする理由
オンライン検定をやりたいと思った方は、何かのノウハウを持っている、あるいは、既に顧客(会員さん)が存在しているのではないかと思います。
オンライン検定は昨今言われている新時代のビジネススタイルである「コミュニティ型」のビジネスに最適なマーケティング活動であるため、今後ますます注目されることでしょう。
さて、そんなオンライン検定ですが、オンライン検定を単に手軽にできる認定試験と位置付けてしまうのはとてももったいなく、しっかりと運営者側のメリットと受検者側のメリットを理解することでこれからの時代に最適な顧客とのコミュニケーションツールとして活用できます。
顧客と最適なコミュニケーションを取り、良い関係を築くことができれば集客に悩むこともなくなります。ビジネスの悩みは集客問題に集約されるとも言われているほど重要なファクターですので、この問題が解決されればビジネスも大きく加速するでしょう。
特に、協会のような社会的に意義のある活動をされている事業者にとっては、その社会性を保ちながら顧客が集まる仕組みを構築できるので、とても相性の良いやり方だと思っております。
具体的に運営者側と受検者(ユーザー)側でどのようなメリットがあるのか、もう少し深掘りして解説していきます。
受検者(ユーザー)側のメリット
受検者のメリットは主にこの3つです。
知識欲を満たせる
知識の習熟度を測れる
(結果、仕事や社会活動に活かせる)
一般的に資格、認定試験、検定などを受ける方は勉強熱心であり、その分野においての専門知識を深めたいという知識欲をお持ちの方々です。
しかし、勉強するにあたり自分自身でゼロから調べて勉強をするのはとても難しく面倒なことであり、もっというとそもそもどこから手をつけて良いかわからない、勉強方法を知らない、という方でもあります。
そこで「検定」の存在意義が出てくるのですが、一般的に検定は知識が体系的にまとまっている参考書や教本のような参考書籍があり、その参考書籍を元に勉強すれば知識を深めることができる仕組みになっています。
さらに、勉強の成果を測る手段として検定試験があるので、ユーザーは試験を受けることで知識の習熟度を把握することができます。
たとえ、趣味の延長で取得するような検定で、その検定を取得することが仕事などに繋がるわけではないとしても、知識を深めることが目的なので、検定が存在すること自体が意義のあることなのです。
運営者側のメリット
では、検定を実施する運営者にはどのようなメリットがあるのかというと、
業界のことや独自のノウハウを広めることができる(認知拡大)
勉強熱心の方々が集まる
(結果、コミュニティを作ることができる)
この3つが挙げられます。
先ほどお伝えしたように、どのジャンルにおいても勉強したいという方が存在しますが、もしあなたが行っているビジネスの業界に検定がなければ、それは、まだまだ業界の認知を広げることができるチャンスでもあります。
加えて、あなたが独自のノウハウやメソッドをお持ちであれば、それを検定として広めることで業界の第一人者としてポジションを確立することもできるのです。
マニアックな検定が集客のカギとなる
また、〇〇検定は基本的にニッチでマニアックなジャンルのものが多く、むしろマニアックなことに価値があるのですが、そんなマニアックな検定を自ら受けに来る方々は運営者にとって貴重な見込み客と言えるでしょう。
例えば「チーズ検定」をわざわざ受検する方は、確実にチーズに興味がある方だと判断することができます。
私たちは度々、集客において重要な役割を担うコンテンツを「キラーコンテンツ」と呼びますが、このオンライン検定をキラーコンテンツに位置付けると、その後の運営もスムーズになると考えています。
不特定多数に向けて当てもなく活動をするよりも、その手前に検定を置くことで、その分野に興味がある人に向けて活動ができるようになりますが、これがビジネスにおいてはとても強烈なパワーを持つのです。
気軽にできるオンライン検定の説明の域を超えて、ビジネス的な考え方やメリットにまで言及してしまいましたが、ここを抑えるとその後の運営や集客活動が楽になるので、ぜひ覚えておいていただければと思います。
検定のオンライン化をする
第一章は概念的なことをお伝えしたので、この章からは少しずつ実用的なことを深めていきます。実際にオンライン検定を実施する際に必要なことをお伝えしていきます。
まず最初に把握していただきたいこととして、オンライン検定を作るにあたり
- 設問、回答など検定そのものを用意する
- 検定をオンライン化する
という2点を準備する必要があります。
①②共に必要ですが、検定そのものを作ることの方が重要事項なので後半で細かく解説するとして、最初にさくっとオンライン化についてやり方をご紹介します。
オンライン化のやり方
検定のオンライン化にあたりシステムを導入していきますが、使っていくシステムは大きく分けて以下の3つに分類できます。
- 提供されている検定システムを使う
- 自分のサイトで検定システムを作る
- 提供されているシステムを自分のサイトに埋め込む
それぞれのメリットデメリットはこちらの表にまとめました。
⑴提供されている検定システムを使う
このやり方が一番ハードルが低くて取り組みやすいやり方です。既に検定の仕組みができていますので、運営者側は設問と回答を用意してシステムに設定するだけで検定を作ることができます。
また、この提供されているシステムの中にも、
- 受検会場でオンライン受検
- 自宅でオンライン受検
という2パターンあります。
イメージとして、「受検会場でオンライン受検」は受検料をいただいてしっかりとした検定をやりたいときに使われることが多く、「自宅でオンライン受検」はエンタメ要素の強い無料の検定をやりたいときに使われることが多い印象です。
⑵自分のサイトで検定システムを作る
こちらはゼロからシステムを構築するパターンで、高度なプログラミングスキルを必要とするので一般的ではないと思われます。ただ、やりたいことは全てできることが1番のメリットで、画面のデザイン、UIUXなど自由に作り込むことができます。
⑶提供されているシステムを自分のサイトに埋め込む
今回私たちが一番おすすめしているのがこちらのパターンです。
特に人気のCMSであるワードプレスの無料のプラグイン「Quiz And Survey Master」で作る検定システムがとても使い勝手が良く、無料の範疇でやりたいことをある程度カバーできる、とても優れたシステムです。
自社サイトがワードプレスで作られている場合はすぐに導入できますし、もしワードプレスを使ったことがないとしても、オンライン検定用にワードプレスを構築して作った方が良いくらい手軽でコスパ良く検定を作れます。
自分のサイトにシステムを埋め込むので、検定用のURLを発行すればスマホや自宅PCで受検していただくことができます。
後ほど検定の作り方のパートで詳しく解説しますが、このプラグインではお名前、メールアドレスなど受験者情報も取得できるのでビジネス的にも優れていると言えるでしょう。
ワードプレスにある程度詳しい方はご自身で仕組みを作れてしまいますので試してみてください。
システム構築のやり方は「」こちらの記事で解説しているのでご参考にどうぞ。
オンライン検定の仕組み作りの5つのポイント
この章ではオンライン検定の設問作りや、検定を集客ツールとして使うときのポイントを解説していきます。
章題を「仕組み作りの5つのポイント」としているのは、検定を作って終わりとせず、それを集客の仕組みとして活用していただくためですので、ご自身に置き換えて読み進めていただければと思います。
受検者の成長を設計する
何のために行われる検定かを考えたときに、そのうちの一つが「受験者の成長」が挙げられます。この受験者の成長を意図的に行えるように検定を設計します。
受検者の成長とは、検定を受ける前と受けた後にどのような変化があるのか考えるとこの設計ができます。また、運営者として「どのような変化をしてほしいか?」という問いに明確に答えられれば、設計も可能でしょう。
また、変化の種類としては、
- 知識的変化
- 心情的変化
- 環境の変化
この3つの変化を促せるような設計ができると満足度も高くビジネス的にも成果が期待できます。
知識的変化
検定を受けることで新しい知識を得ることができたり、知識をより深めることができたりするような設問を設定します。
ポイントとしては、設問自体で知識を深めることができるというよりも、正解の解説文を読むことで知識を深められるようにすると良いでしょう。
受検者は、おそらく回答を悩む設問があると思いますが、それに対してしっかりと正解の解説されていれば大きな学びになり知識的に成長することができます。
心情的変化
こちらは先に事例を紹介します。
日本かき氷協会が主宰する「かき氷検定」という検定がありますが、この検定を受けると自然とかき氷が食べたくなる現象がおきます。
検定を受けることで「〇〇したい」という、なにか行動に移したくなるような心情の変化があると、単に検定を受けて終わりではなくその後も印象深く受検者の心に残ります。
この心情的変化をもたらすためには、堅苦しい設問だけでなくユニークな設問を用意することがポイントです。
環境の変化
環境の変化はビジネス的にも重要なのでしっかりと設計しておきたいところです。
これはユーザー(受検者)のことを考えると設計しやすいのですが、もともとユーザーが検定を受けるメリットは、知識欲を満たせることにあると前述しましたが、ユーザーは検定を受けることでどんどん知識を深めていきたいと思っています。
これまでは勉強の仕方がわからなかったユーザーも、ある検定の存在を知ることで、その分野においての勉強の仕方や知識の深め方を知ることができます。
この変化は「ユーザーにとって勉強できる環境が整った」と捉えることができるでしょう。
オンライン検定の上位級を用意して、もっと知識を深めてもらえるような場を提供しても良いですし、オンライン検定合格者のみに案内する講座や研修を提供しても良いでしょう。
マーケティングの用語で解説すると、
- オンライン検定を「フロントエンド商品」
- 上位級や合格者に案内する講座を「バックエンド商品」
と言います。
このようにマーケティング戦略にも当てはめて検定を作ることができるので、「受検者の成長を設計すること」は、ぜひ覚えておいてください。
設問に意図を持たせる
設問には必ず意図を持たせてください。
意図と言っても最初は難しく考えずに「ユーザーに知ってほしいこと」を基準に設問を考えると良いでしょう。
例えば、ツーリング検定が運営する、バイクに乗ってツーリングを楽しむ人たち向けの検定「ツーリング検定3級」では、
「一般的に海(海抜0m)と山(標高500m)ではどのくらいの気温差があると言われているでしょうか?」
出典:ツーリング検定
という設問があります。
車と違ってバイクは生身で外を走るので外気温を敏感に感じるのですが、気温の変化に対してしっかりと対策をしておかなければ体力の消耗が早くなり運転上支障をきたすことがあります。
なので、気温の変化にはしっかりと気をつけてほしいという意図から、このような設問を用意しているようです。
特に、手軽に行う検定としての位置づけで、知識の習熟度を測るものではない場合は一つひとつの設問に意図を持たせることで教育的要素も強まり、満足度も高くなります。
運営者の想いがにじみ出る設問にする
このような検定の存在意義は「マニアックであること」と「尋常じゃない情熱を感じること」にあると思っており、つまり、運営者の熱意がユーザーに伝わることで共感を生んでいくのだと思います。
一般の方には「そんな検定あるんだ」と思われたとしても、そのジャンルが好きな方には「待ってました!」と思ってもらえるようなマニアックさがちょうど良いでしょう。
その熱意をどうやって伝えるかというと、一つひとつの設問を通じて受検者に熱意を伝えていくのです。
例えば、日本唐揚協会の唐揚検定の設問に
「唐揚げを食べる際のマナーとして「最後の一個」の扱いで正しいものを記号で答えなさい。」
出典:日本唐揚協会
というものがありますが、この設問の答えは一般的なものはなく、唐揚協会が定義した答えがこの検定では正解になります。
このようなマニアックさと実用性を、エンタメ要素を交えて設問にすると受検者が検定中に思わず笑ってしまうような、とてもユニークで面白味のある検定になります。
暑苦しくなくスマートに熱意を伝えられるように設問を考えてみてください。
受検者情報を取得する
「受検者情報」は必ず取得しましょう。特にメールアドレスは確実に取得できる状態が望ましいです。メールアドレスがあれば、アフターサポートとして受検後に様々な情報を送ることができます。
うまく運営されているオンライン検定は必ずメールアドレスが取得できる仕組みになっており、一回きりで終わらないようにサポート体制が整っています。
このようなメールを使ってサポート情報を送ることやご案内を送ることを「リストマーケティング」と言います。リストとは顧客リストのことで、ここでいう受検者情報のことです。
このリストマーケティングは、様々なウェブマーケティングの中でも最もお客様にアプローチしやすいマーケティングと言われており、情報過多の時代になった今、お客様に直接情報をお届けできるという点でとても重要な位置付けになっています。
受検者情報取得のパターン
この受検者情報の取得のパターンとして、
- 受験する前に取得するパターン
- 受験後に取得するパターン
があります。
受験する前に取得するパターン
無料で実施するオンライン検定でしたら、設問の一部として受検者情報の入力フォームを用意すると自然です。
あるいは、検定のお申し込みとして受検者情報を送信してもらうパターンもあります。有料の検定は、有料という特性上、先に料金をいただくことになるためこのパターンが多いです。
このパターンのメリットとして、
- もれなく受検者情報を取得できる
という点があります。
一方デメリットとして、
- 受検者にとっては自分の情報を入力するという心理的ハードルがある
- その結果として受検者数に影響が出る可能性がある
という点があります。
受験後に取得するパターン
受験後、合格者に会員登録を促して受検者情報を取得するパターンがあります。
このパターンのメリットとして、
- 受検者にとっては受験の際に情報を入力しなくて済むので受験のハードルが低くなり気軽に受けてもらえる
- 自ら会員登録をしてもらうので、集まった顧客リストはとても勉強熱心で意欲の高い方々のリストになる
という点があります。
一方デメリットとして、
- 不合格者の受検者情報は取得できない
- 合格者でも会員登録をしない方もいるかもしれない
という点があります。
このようにメリットでメリットはありますが、私たちは事前に受検者情報を取得できる状態にしておくことが望ましいと考えています。事前に情報を取得しておくことで受験者の傾向や試験結果の傾向を見ることができ、それらのデータは検定の改善のために活用できます。
ビジネスの基本として、仮説検証を繰り返しながらより良いものに仕上げていくことを考えると、データを取ることの大切さに納得していただけるでしょう。
“落とす検定”ではない
この記事で解説しているオンライン検定は、その役割としては裾野を広げるためのツールとして考えているので、このオンライン検定受検者はできるだけ多くの方に受けてもらい、そして、多くの方に合格してもらえる方が役割としては効果的です。
とはいえ、合格率が100%になるような簡単な設問を用意しても、それはそれでやりごたえがなくなってしまい、満足度が低くなってしまいます。
このさじ加減としては、初回の受検での合格率を60〜70%程度にして、2回目を受検してくれた方はほぼ100%の合格率になるような仕組みがちょうど良い落とし所だろうと考えています。
何回受けてもなかなか受からない難関検定だと、せっかく興味をもってくれたユーザーが離れてしまう可能性もあるので、ここでの難易度の設計は実は重要なのです。
前述した「全ての設問に意図を持たせる」にも絡んできますが、しっかりと意図を持って設問を用意しなければ、合格率の設計ができなくなってしまいます。
オンライン検定の参考事例
チームエアが関わっていない検定も多いですが、いくつか検定の事例を紹介します。既存のものを見て、「自分の検定に落とし込むとどうなるだろう」と思いながら既存のものを見るととても学びが多いので、ぜひ多くのものを吸収していただければと思います。